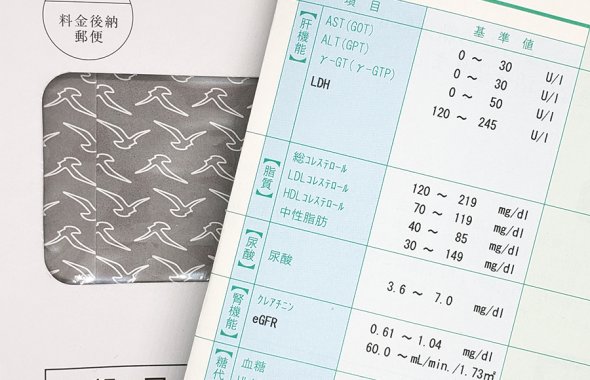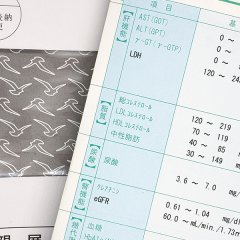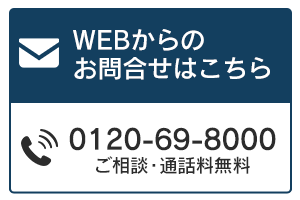B型肝炎の治療法
B型肝炎の治療法は、B型急性肝炎と、B型慢性肝炎で分かれます。
B型急性肝炎
急性肝炎は一般に抗ウイルス療法は必要ありません。
食欲低下などの症状があれば水分や栄養補給のために点滴などをおこないますが、 基本的には慢性肝炎の治療に使う肝庇護薬は使用せず、無治療で自然にHBVが排除されるのを待ちます。
ただし、急性肝炎の中でも、劇症肝炎と呼ばれる非常に強い肝炎が起こり、放置すれば命にかかわる可能性もあると予想される場合には、抗ウイルス薬として核酸アナログ製剤の投与、ステロイドの大量投与や血液を浄化するための血漿交換、血液透析などの肝臓の機能を補助する特殊な治療を必要とする場合があります。
それでもさらに肝炎が進行する場合は、肝移植を行わないと救命できない場合もあります。
B型慢性肝炎
B型慢性肝炎の患者さんに持続感染しているHBVは身体から完全排除することは出来ないことがわかっています。
C型慢性肝炎の場合にはC型肝炎ウイルス(HCV)に対するインターフェロン(IFN)療法、あるいは直接作用型抗ウイルス薬(DAA)の内服治療により、かなり高率にウイルスの増殖を抑えることが期待できますが、HBVに対してはIFNを用いても、後述の核酸アナログ製剤を用いても、現在の治療薬では、ウイルスの完全排除は期待できません。これがHBVに対する治療とHCVに対する治療の根本的な違いです。これをふまえてB型慢性肝炎の治療をすることになります。
HBVに対する抗ウイルス薬
IFN(注射薬)と核酸アナログ製剤(内服薬)の2種類に大きく分けられます。
IFN療法
慢性肝炎の状態にある患者さんが治療の対象になります。
B型慢性肝炎に対するIFN療法は、HBe抗原陽性例に対して週3回のIFNの筋肉あるいは皮下注射を24週間、あるいはHBe抗原の有無にかかわらず、ペグインターフェロンα2a製剤の週1回48週間投与が保険適用となっています。
IFN療法が奏効すればIFN投与を中止してからも、そのままHBVは増殖せず肝炎は鎮静化します。
しかし、IFNの効果が不十分でHBe抗原が陰性化しない症例、IFNを中止するとHBVが再度増えて肝炎が再燃する症例も多く、IFN療法の奏効率は30~40%と言われています。
IFN療法の副作用は、開始当初にインフルエンザにかかったときのような38度を超える発熱・全身倦怠感・関節痛・筋肉痛が最もよく認められます。
ただし、これらの副作用はIFNを継続して投与していくと徐々に落ち着き、数週後には多くの患者さんでは出現しなくなります。
また、白血球、血小板、まれに赤血球の低下が起こります。
これは、IFNが血球を作る骨髄の働きを抑えるためです。
糖尿病の患者さん、また膠原病の患者さんは、症状が増悪することがあります。全員ではありませんが、時に間質性肺炎という特殊な肺炎になる患者さんもいます。間質性肺炎になると稀に命にかかわる場合がありますので、強固な空咳、胸痛などが出現した場合はすぐに胸部レントゲン写真を撮影し、間質性肺炎と診断されればIFNを中止して肺炎の治療が必要です。またIFN療法中に時にうつ病になる患者さんがいます。
うつ病がひどくなると自殺する場合があります。
うつ傾向が出てきたら、すぐにIFNを中止する必要があります。
また、眼底出血、脱毛、タンパク尿などが出現することがあります。
核酸アナログ製剤
直接ウイルスに作用してHBVの増殖を抑えて肝炎を鎮静化させます。
薬に対する耐性ウイルスがいなければ、薬が効いている間はHBVのウイルス量は低下し、肝炎は起きなくなってきます。
肝硬変で常時腹水がたまっている患者さんが、核酸アナログ製剤の長期投与で肝機能が改善し腹水が消失することもしばしばあります。
しかし、IFNと異なり、薬を中止すると多くの症例で肝炎は再燃します。
一旦内服を開始してから患者さん自身の判断で核酸アナログ製剤を自己中止しますと、時に肝炎の急性増悪を起こし、 最悪の場合肝不全で死に至る場合があります。絶対に核酸アナログ製剤を自己中止してはいけません。
核酸アナログ製剤のもう一つの問題点は、薬剤耐性株(変異株)と呼ばれる核酸アナログ製剤が効かないHBVが出現することです。
初期に保険適応となった核酸アナログ製剤では長期投与により3年間で半数近くの患者さんに薬剤耐性株が出現することが分かりました。
なかには、耐性株出現により肝炎が重症化する症例もありました。
しかし最新の核酸アナログ製剤は、薬剤耐性株の出現頻度が非常に低く、また以前の核酸アナログ製剤で耐性株が出現した場合にはもう1種類の核酸アナログ製剤を併用すれば耐性株を抑えることができることがわかり、比較的安全に核酸アナログ製剤が使用できるようになりました。
肝庇護療法
肝炎を抑える目的で肝庇護療法を行うことがあります。
ウイルス量は減少しません。治療薬は内服薬のウルソデオキシコール酸と注射薬のグリチルリチン製剤が一般的です。
いずれの薬剤も軽度の肝障害に対してはある程度有効ですが、B型肝炎特有の急激な肝障害の出現時(急性増悪)には肝庇護剤はあまり有効ではありません。
費用面では、IFN療法と核酸アナログ製剤治療のいずれも、医療費助成制度によって収入額により1万または2万円の自己負担で治療を受けることができ、詳しくは、お住まいの都道府県の担当窓口又はお近くの保健所にお問い合わせください。
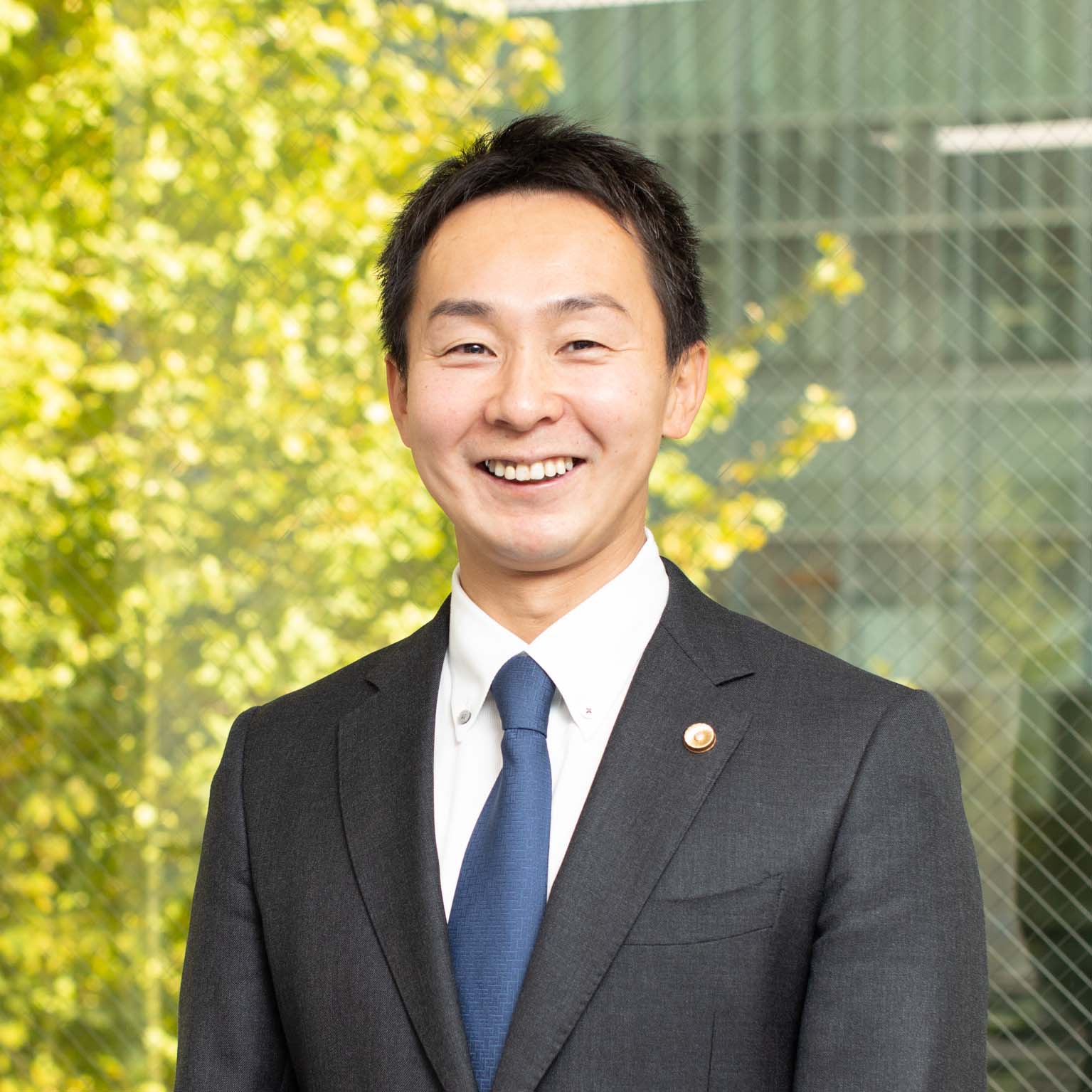
平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。