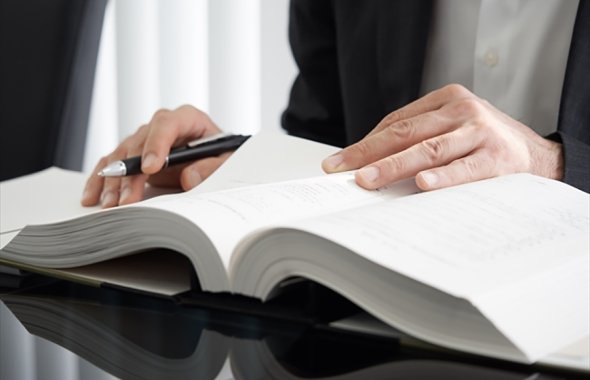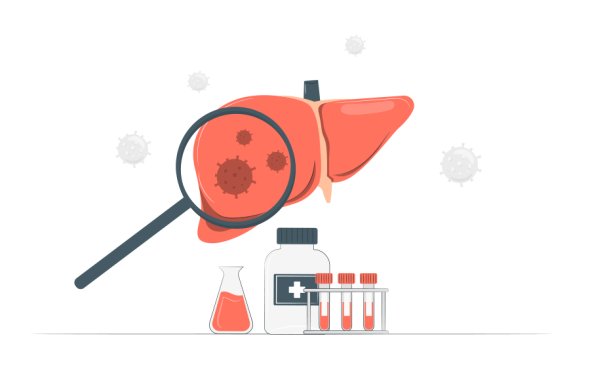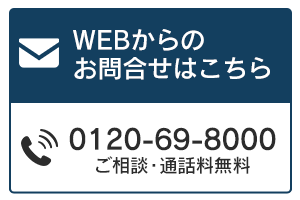B型肝炎の予防治療後の注意点
現在、行われているHBVに対する感染予防は、「HBV持続感染している母親からの出産時感染予防対策によるHBV免疫グロブリンとワクチン接種の組み合わせによる予防」、「医療従事者など、希望者に対するワクチン接種による予防」、「0歳児全員に対するB型肝炎ワクチン(HBワクチン)による予防」が行われています。
HBV母子感染予防対策事業
日本では1986年に開始されました。
HBV持続感染している母親から産道感染で新生児にHBVが感染するため、当初は出産時と生後2ヶ月にHBV免疫グロブリンを、生後2、3、5ヶ月でHBワクチン接種を行うことになっていましたが、2013年10月から早期接種方式(国際方式)へ変更されています。
これは、出生後できるだけ早い時期(12時間以内が望ましいとされています)にHBV免疫グロブリン1mLを筋肉内投与、HBワクチン0.25mLを皮下注射し、さらに、HBワクチン0.25mLを1か月後、6か月後に2回追加接種するスケジュールです。母親がHBe抗原陽性キャリアの場合、旧方式では生後2ヵ月目にもHBV免疫グロブリンを追加投与していましたが、新方式では省略可とされています。
医療従事者などに対するワクチン接種
初回、初回投与1ヶ月後、初回投与6ヶ月後にHBワクチンを接種します。
B型肝炎感染リスクの高い人(HBVキャリアと同居する家族、医療従事者、警察官、消防士など)は、一度はHBワクチンを投与し、その後、HBs抗体の陽性化を確認することが大切です。
HBワクチンの定期接種化
我が国では、1986年から開始されていた従来からの母子感染予防対策事業によって新規のHBV母子感染をほとんど防げるようになりました。
しかし、依然として、ピアスの穴開けやタトゥー(刺青)、性行為等による水平感染や、ワクチン接種を受けていない乳幼児の水平感染の事例が報告されています。
また、ゲノタイプAのHBVは成人が感染してもある程度の割合で慢性化することがわかりました。
そこで、2016年10月から、B型肝炎ワクチンが定期接種化されました。
0歳児に限り、公費(無料)で接種を受けられ、生後2ヶ月から接種可能です。接種回数は3回で、1回目の接種から27日を過ぎてから2回目を接種、さらに1回目の接種から139日を経過した後(20~24週後)に3回目の接種を行うことになっています。
なお、1歳の誕生日の前日までに3回接種ができなかった場合は、誕生日以降の接種は有料となるので注意が必要です。
また、母児感染予防として、出生時にB型肝炎ワクチンの接種を受けたことがある場合は、定期接種の対象となりません。
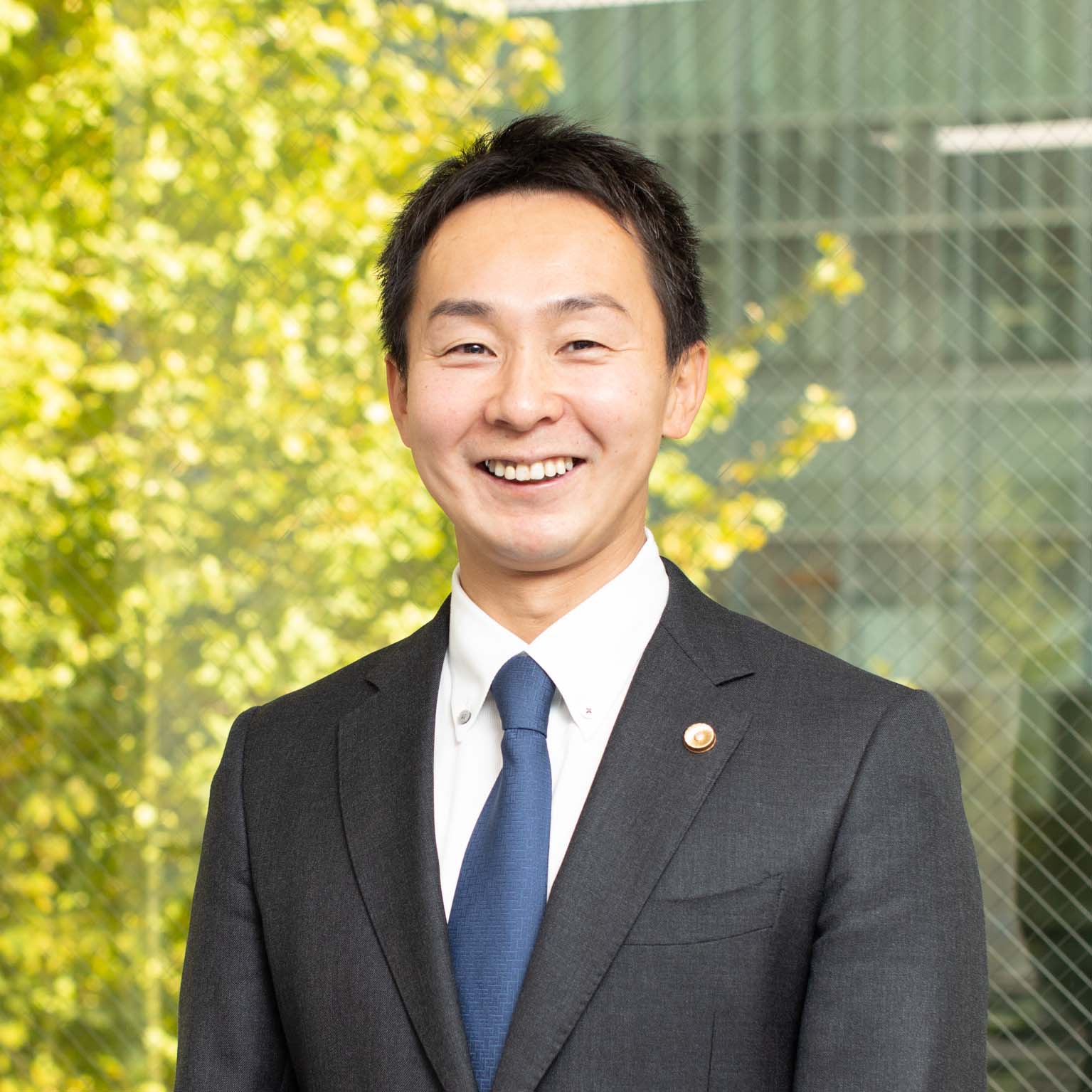
平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。